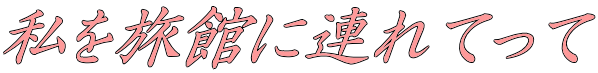
〜経営者の役割〜
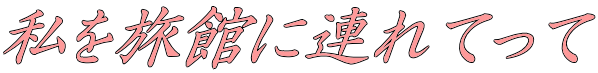
〜経営者の役割〜
| 第12回 経営者のリーダーシップ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
||
 「行ってみたいところがある。それはぬくもりと安らぎ。そして、夢のある場所。」 |
||
| 第12話 「最終話」 | ||
| (1) あらすじ ?
?
? 花壱を閉館し、倫子は東京でコンパニオンの仕事を再開する。バイト中に、かっての花壱の顧客で、神崎開発の会長と再会した。そして、花壱を1日だけ営業して欲しいと提案される。倫子はキャバクラで働くなぎさ、ガソリンスタンドで働く千葉、ラブホテルで働く次郎、ファミレスで働く初恵、駐車場で働く殿山、タクシーの運転手の加賀谷、牛丼屋で働く里子、焼き鳥屋で働く篠田、旅行代理店で働く勅使河原を誘う。
? そして、再び全員が集い、神崎開発の神崎英介社長と神崎会長の親子を花壱に客として迎えることになった。いろいろ策を考える従業員たちに、倫子はいつもどおりのもてなしをしたいという。蛍を見ながら、くつろぐ神崎親子。神崎会長が修善寺の開発計画を見直すように諭すが、神崎社長は計画を変えられない、と静かに言う。ところが、神崎社長は重要な契約書がないと、騒ぎ始め・・・
?
?
?
?
?
?a なぜ、1日だけのために従業員は花壱へ集まってきたのか?
信頼するリーダーである倫子から打ち明けられた計画が成功したら、花壱を再開できるかもしれない。従業員たちは花壱が自分の働きたい場所、一緒に働きたい仲間、やりたい仕事があるから、1日だけのチャンスに賭けて戻ってきた。 ?b 計画は変えられない、という神崎社長の言葉を聞いた倫子の気持ちは?
既に旅館は一度閉館されているのだし、一夜の夢と考えればあきらめがつく。 ?c なぜ加賀谷は大手柄を立てられたのか?
運転手の加賀谷は今回の計画では仕事がなかった。また、従業員の中ではあまり優秀ではない。それなのに倫子が自分を呼んでくれた、大切な仲間として扱ってくれた。ということで、彼の貢献意欲は非常に高かった。それだから、神崎の書類探しを他の従業員が諦めた後、ロビーのソファを直す仕事をし、偶然書類を発見したのである。書類を発見したことは偶然かもしれないが、加賀谷が発見したことは必然だったかもしれない。 ?d 従業員が神崎の書類を取引材料にしようと言った時、「神崎様は神崎開発の社長である前に、花壱のお客様です。」と言って倫子は拒絶したのか?なぜ、従業員は倫子の言葉に従ったのか?
倫子は経営者としての理念、お客様に寛いでもらうサービスを提供する、ことを従業員に説いてきた。そうした経営理念と発見した神崎の書類を交換条件として花壱を存続させることは矛盾するものであり、高邑やチャンスをくれた神崎会長への裏切りにもなる。そんなあくどいやり方で旅館を再開しても、そうした組織文化を持った旅館では客も寛げず、また客は来なくなる。そんな旅館だったら営業を続けても意味がない。彼女は高邑の理念を大切にした旅館にこだわったため、神崎へ書類を返すことを意思決定した。従業員も倫子の理念を共有していたので、彼女の意思決定に従った。 ?e なぜ、神崎社長は気持ちを変えたのか?
花壱にサービスの本質を見出し、同じサービス業を行っている経営者として感ずるものがあったのであろう。また、神崎会長から「地元の反対を押し切って開発を進めるとろくなことがない」という苦言と、ほたるや自然といったその地域にしかない自然の資源を活かした観光開発へビジネス・チャンスを見出したのであろう。 ?f 花壱の営業が再開されて1年、どんなことがあったか想像してみよう。
一度へ閉館した影響が出ているはずだから、客足が戻るまで多少は紆余曲折があったであろうことは否めない。しかし、一度、旅館が閉館して、全員は仕事を失ったという危機を経験し、それを乗り越えて旅館を再開できたということから、花壱への想いはみな強く、それが組織貢献とチームワークを生み、組織としての強さとサービス提供の素晴らしさが、客を増やし、黒字化につながったと思う。篠田と勅使河原の結婚、千葉となぎさが恋人同士へ、他の従業員も少し成長していることから、花壱の営業再開からの1年は充実したものであったと想像できる。倫子は言うべきことはないと言っていたが、1年間でもっとも成長していたのは女将としての十分な能力と信頼を獲得している倫子であろう。 ?g 経営者としての高邑倫子の成長ぶりを評価しよう。
倫子は素人の女将だったからこそ、高邑の優れた理念を愚直に実現しようとし、意思決定してきた。そして、様々な障害も素人ゆえの商売に対する無知、しかし人間の道理としては正しい大胆な意思決定を行ってきた。それが花壱のホスピタリティとサービスを確立し、客や従業員から信頼を勝ち得た。それが彼女の女将としての自信につながり、経営者として成長したのではないかと思う。 |
||
| 2. 経営者の役割 | ||
|
?(1)ビジョンを描き、理念を説き、目標を設定する
?
a 会社と従業員の将来と目標 ?
会社と従業員に将来のビジョンを描き、動機づけする。また、ビジョンを実現するためには、どのような目標があり、それを実現する方法を指示していく。彼女のビジョンは高邑から受け継いだものであるが、それを実現する強い意志を従業員に示し続けた。しかし、具体的な目標の設定はドラマでは描かれていなかったが、42円の黒字でお祝いをしていたことから、月次の黒字が目標だった思われる。 b 組織文化の創造者 組織が教諭する価値観である組織文化の形成には、経営者の価値観や理念が強く影響を与える。そのため、経営者は良い組織文化が形成されるように、価値観や理念を提示していく。倫子は事件が起こるたびに、顧客と従業員を大切にするという姿勢を崩さず、意思決定をしてきた。そうした倫子の姿勢から彼女の経営理念を従業員は感じ、花壱の業績を良くする組織文化が形成されていった。 ?(2)戦略家としての側面
?
a 目標実現のための方法を考える 目標だけではなく、実現の方法としての経営戦略を立案し、それを実行させる役割もある。倫子は戦略立案に関しては、旅館の女将として素人ゆえに関与してこなかった。それを勅使河原が補っていた。 ?
b 環境の変化に対応する組織づくり ?
環境への適応して、組織を作るのも経営者の役割。従業員が柔軟に考え、自律して行動できる組織に花壱も育った。 (3)組織をまとめる人 ?
a 組織を統合する ?
組織の中心として、組織をまとめるリーダーシップが必要。それは最高の権限保持者という制度へ由来するだけでなはく、経営者の能力や人格といったもので組織をまとめる必要がある。倫子の提案で、再び従業員が1晩だけの客のために花壱へ戻ってきたのも、倫子を中心とした組織のまとまりができていたからであろう。 b 組織内外の人を使う ?
組織内部のメンバーだけでなく、外部の人や組織も活用するのも、組織を代表する経営者の務めである。倫子は従業員だけでなく、神崎開発の会長をうまく利用して、花壱を復活させた。 (4)最高責任者 ?
経営者は会社を代表して、従業員、取引先、株主へ責任を持たなくてはならない。倫子は花壱存続のために、自分の信用で消費者金融から金を借りようとしていたが、それは彼女なりの従業員に対する責任の取り方のひとつである。 |
||
| 3. リーダーシップとはなにか? | ||
|
?
?(1)リーダーシップとは?
?
a 意図にあった行動をするよう他人へ促し、実際に行動させるための行為をリーダーシップという。すなわち、人を導くための行為がリーダーシップであり、その行為をする人がリーダーである。経営者は必ずリーダーであるが、組織の中には部門ごとにリーダーもいる。例えば、板場のリーダーは篠田であるが、篠田は倫子の下で働くサブリーダーである。 ?
b リーダーシップの由来 ・制度・・・制度的にリーダーの命令を部下が受容しなければならないようにする ・能力・・・目標達成のための能力が優れた人が能力の優れていない人に指示すると受け入れやすい。 ・状況・・・状況に応じてリーダーシップがきまることもある。サッカーで守備に回ったときは、ゴールを守るキーパーがリーダーシップを取ることが多いのがその例。 人格や資質・・・人格からしてリーダーらしい。 ?
(2)リーダーの資質論 ?
a カリスマ型リーダーシップ・・・もって生まれた資質や過去の教育からリーダーのオーラがあり、それを武器にして組織をまとめる。 ?
b 変革型リーダーシップ・・・過去を断ち切って、未知の新しいことへチャレンジするリーダーシップ。必ずしもカリスマ性は必要ないが、リスク選好的な性格は望まれる。 ?
(3)リーダーシップとパーソナリティ ?
a 専制型・・・自ら決めたことをメンバーに実行させる。勅使河原のリーダーシップ。 ?
b 民主型・・・みんなの意見を聞き、意思決定をしていく。倫子のリーダーシップ。 c 放任型・・・各自に権限と義務を負わせ、任せるリーダーシップ。 |
||
| 4. リーダーシップを有効にする | ||
|
?
?(1)リーダーシップの方向性
?
a 仕事重視(体制づくり・生産性向上)・・・勅使河原のような人 ?
b 人間重視(人間関係・個人への関心)・・・倫子のような女将 c 仕事を重視したリーダーシップを取るか、人間関係を重視したリーダーシップを取るかは、相手の成熟度(能力と意欲)と状況に応じて変化する。そこから、環境適応型リーダーシップの考え方が生まれてきた。 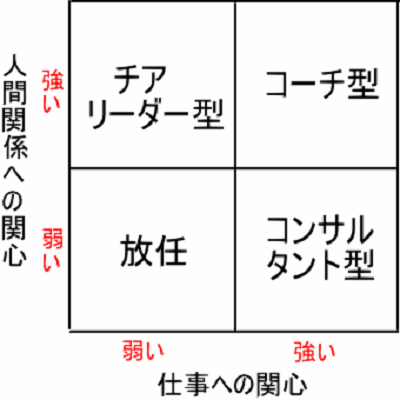 ?
(2)環境適応型リーダーシップ論 a 相手に応じてリーダーシップを変える。部下の能力が高くなれば、指示(命令)的行動を減らしていく。ただし、能力も低く、意欲もないメンバーへは支援するより命令で仕事をさせなくては、目標の成果が得られにくい。能力的に中位程度のメンバーに対して支援的行動を高めてやる。能力も意欲の高いメンバーへは裁量権を与え、結果の義務を負わせて、自由にやらせるほうが、動機づけの面でよい。 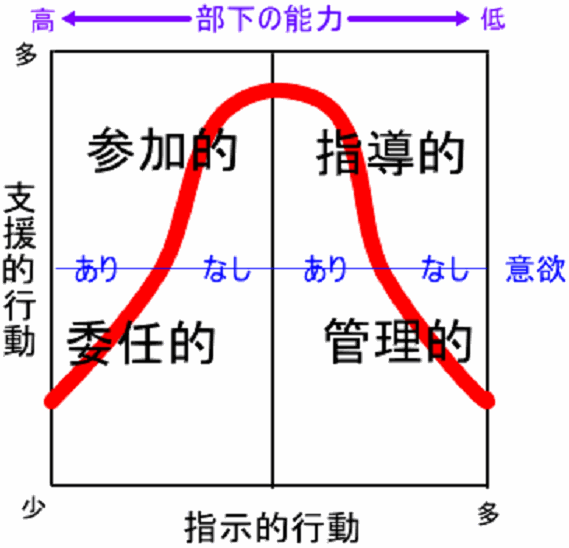 b 置かれた状況に応じて変える。迅速な結果が求められる、環境からの圧力が高い、状況では、能力の低いメンバーには命令で仕事をさせるか、能力の高いメンバーには仕事を任せるやり方が適している。迅速な結果が求められない、環境からの圧力が低い状況であれば、メンバーを育てるようなリーダーシップが望ましい。部下の成熟度が高ければ、部下の意見を尊重し、民主的なやり方が良い。部下の成熟度が低ければ、相手のことを考えた自分の指導プランによって手取り足取り指導するやり方が望ましい。 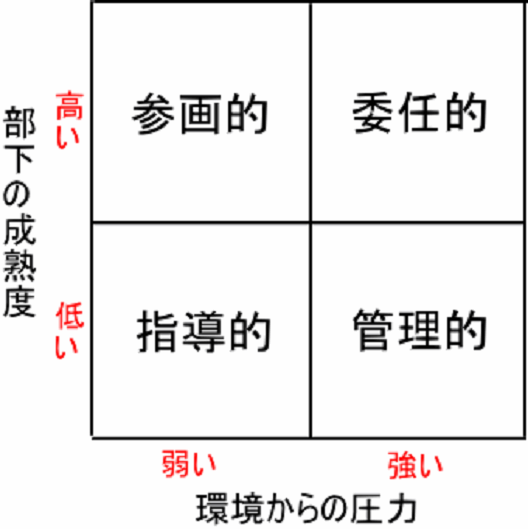 ?
c リーダーシップの代替・・・リーダーシップを行使する状況や相手によってリーダー自体やリーダーシップのスタイルを変えていく。 ?
(3)リーダーシップの有効性 ?
a 正当性・・・リーダーシップを行使する権利に正当性がある。制度、能力、状況などがその理由になる。倫子は高邑の後継者という正当性があったので、素人ながら女将をやり始めた。 ?b 合理性・・・リーダーシップを行使することに合理性がある。能力や状況がその理由になる。例えば、板場でリーダーシップを取る篠田は板長という正当性に加え、板前としての能力が高いから、彼が板場でリーダーシップを行使することは合理性がある。
?c 信頼・・・リーダーシップを行使することに対して部下が信頼している。それは能力や人格によることが多い。ドラマの終盤には、女将である倫子は従業員の信頼を受け、リーダーシップを発揮できる状況になった。
|
||
 |
 |
|