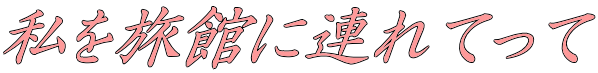
〜経営者の役割〜
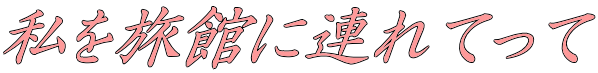
〜経営者の役割〜
| 第1回 旅館という組織 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
||
「行ってみたいところがある。それはぬくもりと安らぎ。そして、夢のある場所。」 |
||
| 第1話 「天国から地獄へ」 | ||
| (1) あらすじ 笹野倫子は24歳のモデル。男からプレゼントを貢がせ、楽しく暮らしていた。そして、TV番組で7つのリゾートホテルを持つGrand Confort Hotel Group社長の高邑隆一郎と知り合い、その財産に惹かれて結婚する。 贅沢三昧の生活を味わっていたが、高邑が3月に出張先のオーストラリアで急逝し、人生が一変する。高邑の多くの財産はオーストラリアの事業の負債を返済するために充てられ、残ったのは伊豆修善寺の寂れた旅館と7,000万円の借金。旅館を9,000万円で買い取りたいという同業者の黒沼の申し出を倫子は受けるつもりだったが… (2) ドラマのポイント a 倫子のような生き方をどう思うか? b 高邑はなぜ、倫子と結婚したのだろう? 高邑が亡くなる直前のメールに、倫子に対する気持ちが表れている。倫子にとっては方便で言った言葉であるが、高邑の本心を初対面で理解したような倫子の言葉が高邑に運命的なものを感じさせたのであろう。 c 旅館の女将の役割とは? 旅館では男は裏方で、看板は女将である。旅館の顔として、営業し、顧客を接待し、従業員に指示をする女将は、旅館のサービスに関わる最高業務責任者(Chief Operating Officer)である。中には裏方の仕事をも統括する最高執行責任者(Chief Exective Officer)としての女将も存在する。 d 桜の木は旅館にとってなんだろう? 高邑が生まれたとき、両親が植えた桜。高邑が誕生日にこの桜の木の下で、みんなに祝ってもらった想い出がある。高邑にとっては、生家であるこの旅館と桜の木は幸せの象徴である。いつか、再び、この旅館の桜の木の下で最愛の家族と大切な従業員と幸せなひとときを過ごす。それが高邑の夢であり、桜の木が高邑の価値観を示している。その高邑の夢である桜の木と旅館を守りたい、という気持ちから、倫子は旅館を続けることにした。これが後の回で説明する組織文化の象徴としての役割を果たすのである。 e なぜ、倫子は旅館を続けようと思ったのか? dで説明。 f あなただったら、花壱をどう立て直すか? ダメになった組織の変革と再生。これはこの授業の主要テーマの一つであるので、後の回で詳しく説明する。ポイントは、授業員間で顧客満足という目標の共有と意識改革、協働(チームワーク)をベースにした業務システムの確立、顧客にとっての価値あるサービスの旅館としての提供である。そのためには、経営者として、ビジョン、経営理念、目標、戦略を明確にし、コミュニケーションで従業員間にそれらを浸透させると共に、動機づけを行う。また、業務内容を分析し、より品質と効率を両立できるような改善策を考え、実行しなくてはならない。例えば、ビジョンは高邑の誕生日には桜の木の下で、従業員で楽しくお祝いをするような、暖かい雰囲気ともてなしの旅館。経営理念は顧客満足と従業員満足を高度に両立する。そのための目標は各自の能力を最大限に発揮して、顧客をもてなし、多くの顧客に来てもらう。そして、利益をあげて借金を返済する。戦略は老舗旅館の特徴と料理の美味しさを活かし、女性客向けに高級志向で売っていく。各従業員の暇な時間をなくすように、業務分担を見直すなどを行っていくことであろう。 |
||
| 2. 日本の旅館業界 | ||
| (1) 旅館軒数は減少気味。ホテルは増加傾向。 これは日本人の生活が西洋化し、西洋スタイルのホテルが好まれるようになったのであろう。また、家業で旅館をやっている中小旅館は、後継者不足で廃業するケースも多くなっている。最近はバブル期の投資が、その後の不況で回収できず、経営破綻する旅館もある。舞台として使用されている落合楼も民事再生法を2002年に申請した。 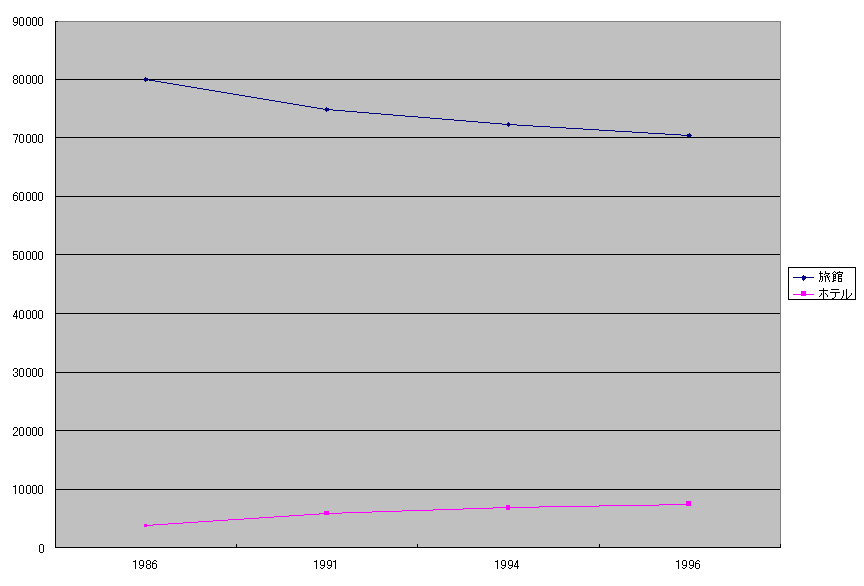 (2) 旅館の1軒当たりの平均部屋数は14部屋と多少大型化。これは中小旅館が減少してる影響と考えられる。 (3) 個人旅行者の宿泊料、パック料、宿泊日数は伸びており、そうした恩恵も一部の人気旅館以外にはいっていないのかもしれない。 (4) ホテルを選好する人55%、旅館は45%。年齢が高くなると、旅館を選好する比率が多くなる。そのため、旅館の顧客ターゲットを中高年者へ絞り込む戦略か、ホテル的なサービスやホテルにない独自性で若い顧客層を開拓する戦略のどちらを採用するかで、経営は変わってくる。 (5) 最近の顧客ニーズは、料金割引、個性ある料理、観光案内サービス、イベント、ゆったりした浴場などである。特に温泉と露天風呂はぜひとも欲しい。また、料理も高級なモノでなくても良いが、地元の新鮮な食材を使ったスローフードを目玉にする旅館も増えている。旅館単独でなく、旅館街として黒川温泉のような共同入浴システムなど、協働して地域の競争力を高める例も見られる。 (6) 旅館経営の成功の鍵(Key Factor for Success)は、設備(客室、温泉、雰囲気)、料理、サービス、近隣の観光資源と考える。 |
||
| 3. 組織とは? | ||
| (1) 個人の事業活動と組織の事業活動の相違 個人という一人の力ではできることが限られる。複数の人間が集まって、協力し合えば、一人で事業をするときとは違った大きな事業もできる。組織は協働システムと言われる由縁である。それが組織のメリットだが、組織の中の人をまとめ、力を発揮することは難しく、そこに組織のリーダーとしての経営者の力量が問われる。 (2) 組織の定義 a 社会的存在 b 目標によって動いていく c 意図的に調整された活動のシステム d 組織の外部との相互作用の中で活動していく(オープンシステム) (3) 組織の重要性 a 資源を集め価値を生み出す変換プロセスへ投入し、目標を達成するために価値を産み出す。 b 個人ではできない価値を産出する。 (4) 組織が成立する要件 a 共通の目的 組織のメンバーがばらばらの方向に向かって仕事をしても、組織としての良い結果は生まれない。そこで、組織の目的をメンバーへ与え、その方向に向かって働いてもらう必要がある。 b 組織メンバーの共通目的に対する貢献意欲 共通目的があっても、それに対してメンバーが貢献しようと言う気持ちがなければ、共通目的を達成できない。そのため、メンバーが共通目的にコミット(責任をもって仕事を成し遂げる)し、貢献をしたくなるように、動機づけが必要である。 c 組織メンバー間のコミュニケーション 組織というのは、協働システムなので、経営者・管理者・従業員間の意志疎通が重要である。自分の意思を相手に伝え、それで行動してもらうためには、相手の考えを知っておかなければならない。 (5) 旅館組織にとっての女将の役割 上述したとおり、女将は旅館の顔であり、花壱ならば経営者兼オーナーである。 (6) 花壱は組織として有効に機能しているか? a 事業の運営・・・仕事のやり方、仕事への姿勢がなっていない。それは組織としての共通目的がメンバーに理解されておらず、各自の仕事を惰性で行い質も悪く、組織としてのチームワークも見えない。 b 戦略・・・戦略とは、組織の経営資源と外部環境を適合させるための、シナリオである。どんな旅館にしたいのか、そのためにどうしたら良いかが見えない。高邑が旅館を買収し、高邑が経営戦略を打ち出す前に急逝した。そのため、経営戦略が不在のまま、花壱は日々の業務をやっているだけである。 c ビジョン・・・どんな旅館にしたいか、という将来像がビジョンである。ビジョンは目指す方向、目的、理念を内包したイメージである。良いビジョンはメンバーへの動機づけになる。 |
||
| 4. 事業継承 | ||
| (1) 事業継承するか廃業か? 事業継承をすべきかどうか、という判断は、1つは後継者がいるかという視点。もう1つは会社(組織)の財務状況が債務(借金)をどの程度あるかで判断する。その分析結果によって、事業継承、社員による事業買収であるMnagement Buy Out (MBO)、事業の売却(M&A)、営業譲渡、廃業というような意思決定が行われる。この段階での花壱は後継者として一応倫子がいるもののやる気はないし、能力もない。借金も多く、赤字経営だから、廃業にするのが一番良いかもしれない。 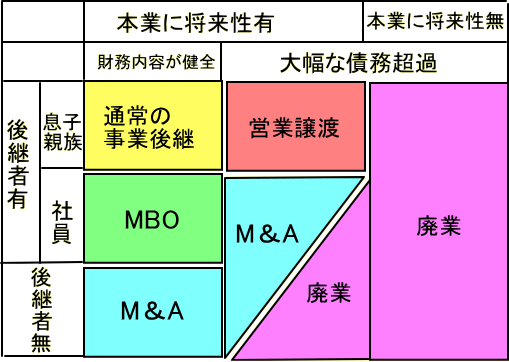 (2) 事業継承とは? a 目的・・・これまで築き上げた事業という財産を後世にまで残すために、事業を引き継いでいくこと。 b 相手・・・オーナー会社や家業の商売は子供、妻、親戚といった血縁者、社内の人間、親会社、銀行、取引先といった外部の人に事業を継承してもらうこともある。最近では、事業を他社へ売却する例も出ている。 c 継承するもの・・・営業権、資金、人材、知識、固定資産と流動資産等。 (3) 事業継承のポイント a 事業継承は経営の踊り場になりやすい・・・事業継承と共に経営のやり方が変わって失敗したり、また、事業継承がうまくいかず、経営の踊り場になってしまうこともある。 b 後継者が事業継承しやすいような環境の整備と教育を行う。現職社長が後継社長に帝王学を学ばせて教育する。また、後継者が十分な手腕を発揮できるように、古参幹部を引き連れて現職社長が引退することや、取引先への根回しをおこなうなど、現職社長が行う。 c 子供への事業継承のポイント・・・経営者としての能力だけでなく血縁で事業継承する世襲は時代遅れだが、従業員数が少ない中小企業では世襲がもっともしっくりいくことも多い。引退する社長はスケジュールを決め、準備をしていく。子供への継承を考える場合は、早い時期から後継社長を周知させておく。後継者の教育は社内で行っていく。黒沼旅館の社長のように、息子を重要な仕事の場に連れて歩いて、教育をしながら、社内外に自分の後継者であることを認知させるやり方は評価できる。あまり優秀そうでない息子であるが。 d 事業継承と相続の問題・・・オーナー企業の場合、財産の相続と事業継承が密接に関わっている。そのため、財産相続の評価額や納税額を把握しておく。会社の株式などは分散しないように、後継者の子供へ集中する必要があるが、相続問題で社内を巻き込んだトラブルにならないように配慮が必要である。特に社内に血縁者が働いている場合は要注意。 (4) 花壱の事業継承の分析 a 高邑が急逝したため、事業継承の準備がなされなかった。従業員も突然、倫子がオーナーと言われ、面食らっている。 b 旅館経営に素人である倫子が遺産相続として事業を継承することになってしまい、経営者としての事業継承が考慮されていない。 c 事業内容と旅館の資産を吟味せず、倫子が事業継承することになった。 d 悪い事業継承のやり方である。 |
||
 |
 |
|