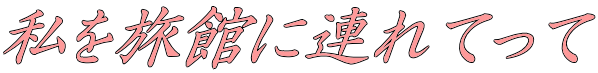
〜経営者の役割〜
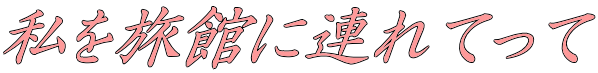
〜経営者の役割〜
| 第7回 動機づけの理論 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
||
 「行ってみたいところがある。それはぬくもりと安らぎ。そして、夢のある場所。」 |
||
| 第7話 「母親失格」 | ||
| (1) あらすじ ? 倫子は黒沼へ支払う借金返済をできず、困り果てる。そこで、なぎさは倫子に惚れている黒沼法生とデートし、法生から父親に借金返済を待ってもらうアイディアを考えつく。ところが、デート場所にいた千葉が切れて法生を殴ってしまう。
? 加えて、法生が持っていたレストランの売り上げがなくなっていることがわかり、黒沼利一は金子が盗んだに違いないから、千葉をクビにするよう迫る。千葉が事情を知り、千葉は旅館を辞めると言い出すが、倫子は千葉を信じて黒沼の要求を断る。一方、法生とデートしたことが街の噂になり、倫子の義理の娘である志保が怒る。
?
?
?
?
?a 借金返済を依頼するため、法生とデートする倫子をどう思うか?
今までの倫子の生き方からすれば当然の結論なのかもしれない。 b 金を盗った千葉をクビにしろ、という黒沼の要求を倫子はどう処理すべきか? 花壱にとっては黒沼は大口の債権者。だからといって理不尽な要求を受け入れる必要はない。ただ、金を誰かが取ったということになればこれは犯罪であるから、まず、警察に行くことが筋である。警察の捜査の結果、万が一、花壱の従業員が犯人であったのであれば、花壱としてその従業員を懲戒解雇すればよい。事実が判明しないうちに、慌ててもしょうがない。 c 倫子と志保の間は、なぜ、うまくいかないのか?どうしたらうまく行くか? 根本にあるのは倫子に対する不信感と父を盗られた嫉妬。後者を払拭するのは難しいが、前者はコミュニケーションを取り、志保へ理解を促していくことが重要である。両者に信頼関係が形成されれば、志保への動機づけなどで両者の人間関係は良好になっていくであろう。 d 千葉を信じ、借金返済の延期を断った倫子の意思決定をどう考えるか? 千葉が金を盗んだという証拠はなく、従業員を信じると言う意思決定は正しい。しかしながら、千葉を信じ、借金返済延期を断らず、借金の返済延期の道も残しておくべきであろう。すなわち、千葉の無実を警察などの第三者に明らかにしてもらう。そうなれば、証拠もないのに千葉を犯人扱いにした黒沼は、花壱の借金返済延期を飲まざるを得ないであろう。 e 「パパがいたとしたら同じことをしたと思うよ」という志保の言葉を組織論的にどう解釈できるか? 高邑は花壱の基盤になる理念を打ち出した。その人と同じ意思決定を倫子が行ったと志保が評価したと言うことは、倫子を高邑の正当な後継者であると認めたと考える。 f 倫子と志保の関係は少し変わったが、なぜ変わったか? 高邑に対する倫子の想いを志保が理解し、両者の間に横たわっていた不信感が解消したことで二人の関係は良好になっていくであろう。 g 千葉をクビにしなかったことで、千葉や花壱どう変わると予想されるか? 信頼される、というのは、今まで信頼されたことがあまりない千葉にとって、花壱や倫子に対する貢献意欲は高まる、大きな動機づけになろう。また、千葉を信じ、守った倫子を他の従業員は信頼するであろう。それが経営者としての倫子を認める大きな動機づけになろう。 |
||
| 2. 動機づけのメカニズム | ||
|
?
??
(1) なぜ仕事をするのか ?(3) 「人間関係論」byメイヨー
1920年代に行われたGEホーソン工場で行われた実験から生まれた理論で、良好な人間関係がやる気を引き出すという結論が導き出された。しかし、人間関係は動機づけの一要因に過ぎない、という批判がなされた。 (4)「欲求階層説」byマズロー マズローは人間の欲求が下図のように階層的になっており、下位の欲求が満たされると上位の欲求へ関心が移るとしている。非常にわかりやすい理論で、説得力も感じられるが、人間の欲求は整然と階層になって欲求の高次化していく、というのは現実的ではないという批判がなされた。例えば、篠田は十分な給料を得ておらず、生理的欲求が満たされているとは思えないが、自己実現が追求できる花壱へ戻った。こうした、アトランダムな欲求に関しての説明を、マズローのモデルでは説明できない。 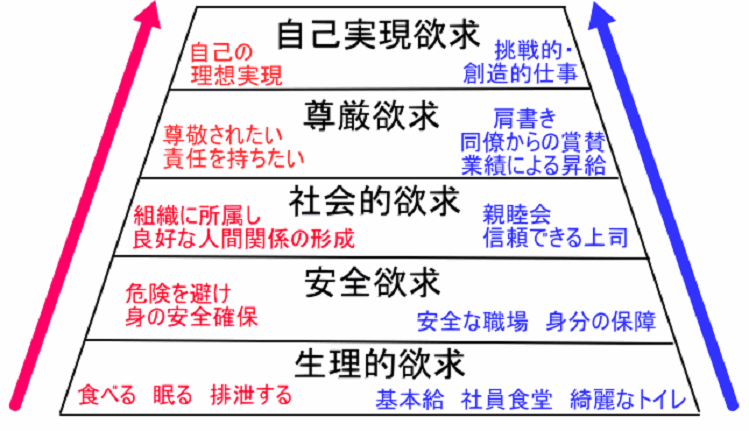 (5) 「X理論Y理論」byマグレガー
a X理論・・・従来の組織における性悪説に基づく人間観で、従業員は主体的に働きたがらないし、責任も持ちたがらないから、飴とムチで管理しろという管理手法が望ましい。かっての花壱の従業員を見ていると、彼らはX理論の人間観にぴったりのような気がする。 b Y理論・・・人間は仕事の内容によっては進んでやるし、責任も持ちたがる、という人間観。そこからの管理は職務の内容を多様化する職務拡大と、権限を委譲するなどの職務充実などが提案される。このドラマでは、従業員たちが徐々にY理論の人間観になっていくのはおもしろい。 (6) 「マクレランドの理論」byマクレランド 欲求を達成欲求、権力欲求、親和欲求に分類し a 達成欲求の強さは職務業績と強く相関するが優秀な管理をするかどうかはわからない b 親和欲求と権力欲求の強さは管理能力の高さに相関する c 権力欲求が強く、親和欲求が弱い管理者がもっとも高い業績をあげた という結論が導き出された。 さて、倫子は親和欲求が強く、高邑の想いを残したい、実現したいという達成欲求は強い。マクレランドの理論からすると、倫子は必ずしも優秀な管理者とは言えない。 (7) 「動機づけー衛生理論」byハーズバーグ a動機づけを衛生要因と動機づけ要因に分類し、衛生要因は不満の予防につながり、動機づけ要因は仕事のやりがいにつながる、という結論をくだした。 b 衛生要因=賃金、労働環境、人間関係、仕事以外の外発的要因 c 動機づけ要因=仕事の達成感、他者の評価、仕事の内発的要因 篠田は彼にしてみれば低賃金で労働環境も良くない花壱では不満も多いであろう。しかし、勅使河原との人間関係の良さがその不満を緩和し、花壱にとっては欠かせない人材ということで尊敬され、コストの制約はあるにせよいろいろな料理にチャレンジできることから動機づけは十分できていると思われる。そのため、不満はあるものの、花壱に貢献したいという動機づけがなされている。 |
||
| 3. プロセスに注目した動機づけ理論 | ||
|
?
?
(1) 「公平説」byグッドマン&フリードマン
職務に対する労力とそこから得られる報酬を天秤にかけ、そのバランスが他者や経験上公平と評価されていることが動機づけになる。 (2) 「強化説」byルーサンス、ハムナーら 人間の学習効果により。適度な報酬は動機づけになるが、報酬がなかったり罰せられたりするとその行動は控えられてしまう。 (3) 「期待説」byポーター&ローラー 人間行動は努力が報酬につながる期待と、報酬の魅力によって決まるという、動機が形成される過程を論理立てて説明したモデル。与えられた目的に対して、過去の経験や与えられた情報から達成すると満足するという期待の下で努力をする。努力に本人の能力と資質、自分はその仕事で成果をあげなくてはならないという役割の知覚が加わり、業績があがる。業績は努力によってもたらされるという期待が、次の努力を生む。業績の結果、経済的、精神的報酬を得、満足する。それが、思っていた報酬どおりであれば、次の努力に結びつく。 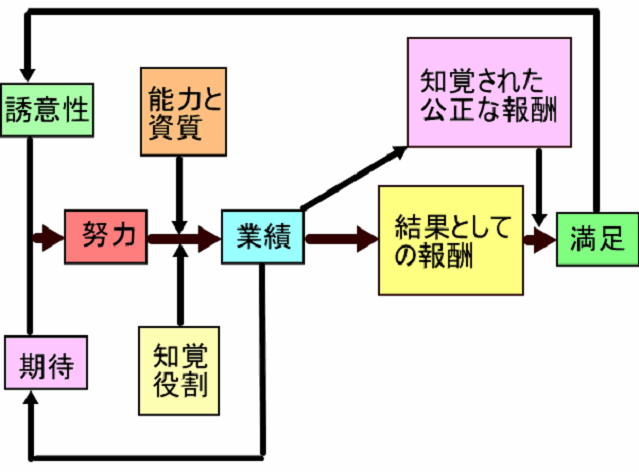 例えば、花壱の従業員は客が増えれば給料が上がるという誘因(誘意性)を倫子から与えられている。また、自分たちが努力をすると、顧客が喜んでくれる、ということをこれまでの第5話と6話から学習している。そこで、客を増やすために努力をすると、実際に客が増え、売上も増える。それが努力をすれば、結果がついてくる、という期待を感じ、次の努力を導き出す。また、業績の結果から得られる経済的報酬(給料の増加など)や、客から誉められることや雑誌に掲載されるなどの精神的報酬を獲得し、それが自分で思っている報酬として適切だと思えば、満足につながる。それが次の努力を引き出す誘因になる。 (4) 「目標設定モデル」 人間は自己成長の欲求があるため、より困難な目標のほうが動機づけが強くなる。 |
||
| 4. 部下のコミットメントを引き出す | ||
|
?(1) コミットメントとは?
ある仕事の目標を責任もって果たすことでの貢献。 (2) 組織へのコミットメントを引き出すには? a目標の設定と共有 コミットする対象が曖昧だと、貢献する方向を誤る可能性が高くなる。目標が明確化されても、共有されなければ、貢献を引き出せない。 b権限委譲(Enpowerment) 責任を与えられるだけでなく、権限を与えなくてはいけないのは、三面等価の原則でお話した通り。権限が与えられると仕事を進めやすくなる、動機づけになる、といったメリットがある。反面、上司は権限を与えっぱなしにするのではなく、適切な指導と管理をしなくてはならない。 cサポート 与えられた仕事をやる気だけでこなせるわけではない。そこで、部下が与えられた仕事の目標で成果をあげられるよう、支援もしっかりしなくてはならない。 d評価とフィードバック 仕事の成果を認め、評価することは、次の仕事への動機づけと課題の明確化になる。 (3) 適切な動機づけ a なにが誘因なのか? 部下は多様であり、共通の要素はあるものの有効な動機づけは異なる。そこで、なにが部下のやる気を引き出す誘引になるかを上司は分析しなくてはならない。 b 仕事の成果を誘因へ反映する 仕事の成果を期待につなげるため、誘因へ反映する。 (4) 信頼をベースにした経営者と従業員の関係形成
信頼がなければ、経営者と従業員のコミュニケーションを図れないし、動機づけも有効に機能しない。いわば、マグレガーのY理論を前提にして、動機づけを行っていく必要があるのではないか。 |
||
 |
 |
|