| 第8回 「信頼のリーダーシップ」 1話 2話 3話 4話 5話 6話 7話 8話 9話 10話 11話 |
||
| 1.第6話 | ||
| (1) あらすじ 二階堂は恋人の稲葉からプロポーズされるが、仕事を選ぶ。ハンパ課はシンデレラプロジェクトを役員へプレゼンテーションを行う事になったが、試作品が完成しない。林田は納得のいく試作品を作るため、徹夜する。そして、ハンパ課の夢であるシンデレラがついに完成し、プレゼンテーションに挑むが… (2) ドラマのポイント A なぜ、二階堂は林田の工場を立ち去ったのか? これまで北野は有言実行だったので、北野を信頼して試作品の生産に関わる業務は任せ、林田の工場を立ち去った。上司は部下の行動に対する責任を負わなければならないから、どうしても部下を監視したくなる。しかし、監視される部下からすれば、そのような上司の行動は働く意欲を削ぐことになる。また、複数の部下を持つ上司は、四六時中一人の部下についているわけには行かない。そこで、上司は部下に仕事を任せ、監視や細かい口出しはしない。部下には報告、連絡、相談を徹底させ、仕事に支障がある場合のみに上司が出ていく方法が取られる。二階堂は「信じてなきゃ一緒に仕事が出来ない。同じ夢を追えない。」と言うが、コミュニケーションを良く取り、信頼を働く者同士で築き上げ、仕事を任せていくことで、一人ではなし得ない仕事をしていくのである。 B なぜ、北野は林田の側から離れたのか? 北野は林田がきちんと仕事をしているかどうかを監視しに来たわけではなく、シンデレラの試作品製造の手助けしたいという善意の気持ちであり、完成を林田と一緒に喜びたいという仲間意識から工場へやって来た。しかし、試作品を作っている林田から、信頼して欲しいと言われ、北野は監視をしているわけではないのでその場を離れた。 C なぜ、二階堂は稲葉と別れたのか? 東亜ケミカルとの一件から、稲葉のことを信じられなくなった。また、シンデレラの企画に熱中しているハンパ課員のやる気を削ぎたくなく、また、二階堂自身もシンデレラの企画を途中で放り出したくなかった。 D ハンパ課の雰囲気はどう変わったか? シンデレラプロジェクトの成功という1つの夢に向かって、意欲を持って自分のすべき仕事を一生懸命やっている。そのため、ハンパ課は信頼感で結ばれた強さと、仕事に対する情熱が感じられるようになっている。 |
||
| 2.動機づけ理論〜欲求説〜 | ||
| (1) 人はなぜ働くのか a 受動的=仕事が義務とか目的のための手段である場合 b 主体的=誘因に反応して自ら働く (2) 動機づけとは何か 人に対して働く事への誘因を与えること (3) 「人間関係論」by メイヨー General Electricのホーソン工場で行われた実験から、良好な人間関係がやる気を引き出す、という結論をメイヨーらの研究者が導き出した。 (4) 「欲求階層説」by マズロー a 欲求が階層になっていて、下位欲求が満たされると順次より高次欲求をみたしたくなるという理論。欲求は低次元のものから生理的欲求、安全欲求、社会的欲求、尊厳欲求、もっとも高次元の欲求は自己実現欲求である。 b 生理的欲求を満たす誘因=給与 ↓ c 安全欲求を満たす誘因=職場の物理的環境 ↓ d 社会的欲求を満たす誘因=職場の良好な人間関係 ↓ e 尊厳欲求を満たす誘因=職位や表彰 ↓ f 自己実現欲求を満たす誘因=やりがい 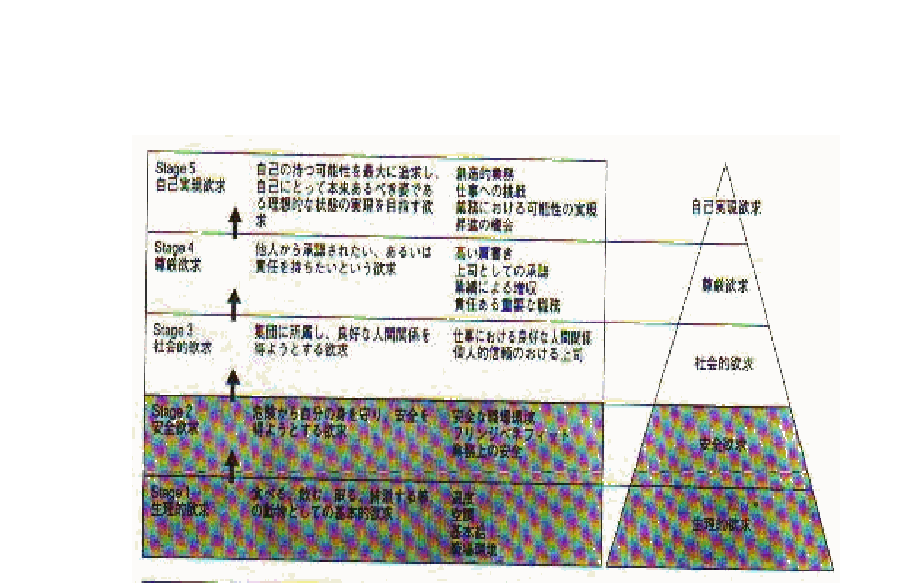 (5) 「ERG理論」by アダルファ マズローの欲求階層説を3段階にまとめたもので、存在(Existence)欲求→関係(Relatiosn)欲求→成長(Growth)欲求と欲求は3階層になっている。 (6) 「動機づけー衛生理論」by ハーズバーグ a ハーズバーグは欲求というのは、階層的ではなく、順次高次元欲求を満たそうとするものではないと批判した。そして、動機づけには不満を抑える衛生要因と、満足を与える動機づけ要因があるとした。 b 衛生要因=賃金、労働環境、人間関係、仕事以外の外発的要因 c 動機づけ要因=仕事の達成感、他者の評価、仕事の内発的要因 |
||
| 3.動機づけ理論〜過程説〜 | ||
| (1) 「公平説」by グッドマン&フリードマン 公平に扱われているか、評価されているかが動機づけになる (2) 「強化説」by ルーサンス、ハムナーら 適度な報酬は動機づけになるが、報酬がなかったり罰せられたりするとその行動は控えられてしまう。 (3) 「期待説」by ポーター&ローラー 動機づけ(誘位性)と期待によって人は努力をするようになり、結果に対する報酬に満足すれば、それが次の動機づけにつながる。 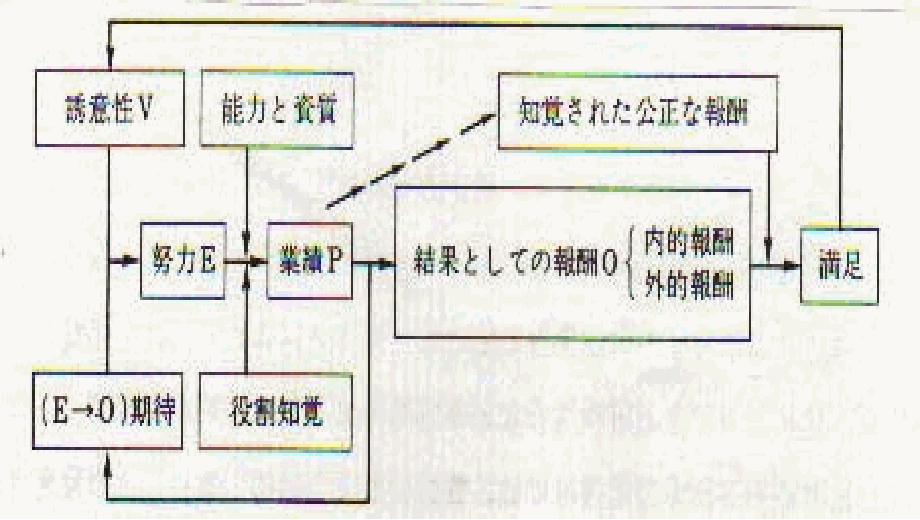 (4) 「目標設定モデル」 自らが決定権のある場合、動機づけが行われる |
||
 |
 |
|
