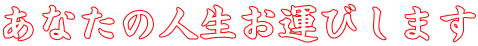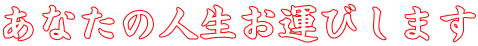第6回 会社の経営戦略
|
| 第6話 「あっけらかん離婚大騒動」 |
(1) あらすじ
アーム引越しセンターは電話もトラックも増え、売り上げも順調に伸びていた。
ある日、はこれから離婚するという夫婦の引越しを請け負う。夫婦共働きだったため、仕事のパートナーとしてはこれからも関係を続けるが夫婦として離婚するという。
二人の子供は、夫と妻がそれぞれ引き取り、家具も二等分。子供たちも離婚の事を納得しているとあっさり話す夫婦に疑問を持つ真喜だが、引っ越し当日、誰も予想できなかった出来事がおこる・・・
(2) ドラマのポイント
a 電話代20円を渡すサービスをどう思うか?
アーム引越センターの経営理念は顧客満足の追求で、ビジョンは世界一の引越屋である。その理念を追求するための経営戦略として、他社と違ってきめ細かいサービスによる差別化である。きめ細かいサービスを印象づけるための戦術として、ユニフォームの採用、新しい靴下による作業、女性の作業員による引越、梱包用新しい段ボール箱の使用、電話や電気の契約変更代行サービス、見積もり時の電話代20円お返し、オプションでの荷造りサービス、地元商店街と提携した家財道具の販売などが戦術としてある。事前見積もりや行き先別の荷物識別は作業効率化のための工夫であり、社名と電話番号0123は広告上の工夫である。こうした全ての戦術は差別化の戦略を顧客に対して明確にアピールすることで、心配りに溢れたサービスは感動を顧客に与える。アーム引越センターのサービスによって感動した顧客は、次に引っ越しする時もアーム引越センターへ依頼しようという気持ちにもなるし、また、友人達に自分の感動を伝えようとする。覚えやすい社名と電話番号で新規顧客を獲得し、感動を与えるサービスで、顧客をファンへ育成する顧客維持型マーケティングの戦略である。この時代の引越業は社会であまり認知されておらず、使う機会が少ないだけに、体験者による口コミは非常に効果的な広告になる。アーム引越センターの感動を与えるサービスは、口コミになりやすいし、顧客創造型マーケティングの視点でも優れていると言える。
b 今までの仲間など従業員が増えたことで、アーム引越センターにどのような問題が生じると思うか?
上原夫妻、愛子と久美子、助ちゃんというコアのメンバーに、賢太郎の幼なじみたちが加わって、業務処理能力は高まる。真喜の経営理念を共有し、お互いに良く知っている同士なので、コミュニケーションは問題ないものの、ビジネスと友人関係の割り切りが課題になる。今後、求人募集をして、顔見知りでない従業員が入社してきたとき、組織のまとまりを生み出すことが課題として生まれるであろう。
c 「荷造りご無用、0123、アーム引越センター」というコピーをどう思うか?
洒落たコピーではないが、アーム引越センターのサービスの特徴(「荷造りご無用」)、連絡先の電話番号、社名が短い文章の中に入っていて優れている。
|
| 2. 企業のアイデンティティ |
(1) アイデンティティの必要性
企業がアイデンティティを持つことで、同業他社がひしめき合う業界内で、他社との差異を示し、顧客や取引先から選好してもらいやすくなる。
(2) 目に見えるアイデンティティ
a 他企業と明確に区別される独自性を企業のアイデンティティ(Corporate Identity)という。
b 名称・・・もっともわかりやすいのが名称。似たような社名が多いと埋没する危険性あり。独自性があり、その企業の事業分野や理念が明確になっていて、わかりやすい社名が望ましい。
c シンボルマーク・・・社名をイメージ化したシンボルマークもアイデンティティになる。例えば、日本航空はかつて鶴のマークを使用していたが、鶴=日本の鳥=日本の翼=日本航空、という企業のアイデンティティを示すものであった。
d 製品やパッケージ・・・コカコーラの有機的なボトルは、あれ自体でコカコーラという企業を識別させる。
e 広告・・・同じような広告をずっと行うと、広告自体で企業が識別できる。例えば、「ファイト!1発!」というかけ声と共に青年が困難を乗り越えるリポビタンDのCMは、大正製薬のアイデンティティをなっている。
(3) 目に見えないアイデンティティ
a 経営理念・・・鉄は国家なり、という新日本製鐵の理念は、企業のアイデンティティとして機能していた。
b 企業文化・・・同じ業界でも企業ごとに異なった企業文化があり、それがアイデンティティになる。
(4) アイデンティティ構築のポイント
a 自己と他者にとって価値あるアイデンティティを作る。例えば、三菱自動車のリコール隠しをした企業というアイデンティティは、顧客にとって不利益にしかならず、会社側にもマイナスにしかならない。
b 整合性と一貫性をもたせることで、アイデンティティの拡散と混乱を防ぐ。
|
| 3. 経営戦略とは? |
(1) 経営戦略の意味合い企業と事業環境の適合性を描くこと
a 企業と企業を囲む環境の適合をさせるための指針
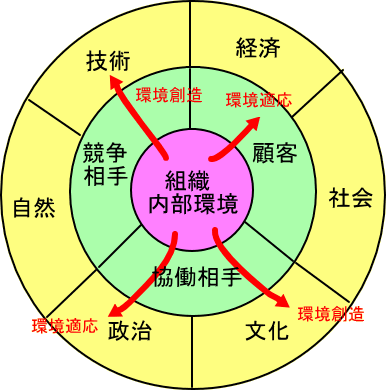
b 企業の持っている経営資源の調達と使い道を考える
c 顧客、競争相手、共同相手、経済、政治、技術、社会、文化、自然環境の変化に会わせて、企業が活動していく方法を変化させていく。
(2) 経営戦略の種類
a 全社戦略、事業戦略、機能別戦略
b 成長戦略、競争戦略、撤退戦略
(3) 戦略策定プロセス
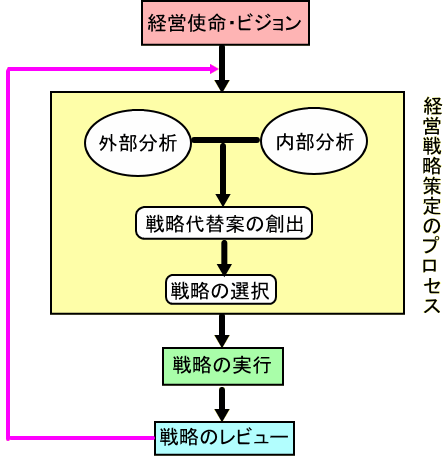
a 外部環境分析・・・顧客動向、競争相手の動向、取引先の動向を中心に分析し、自社にとってどんなチャンスと危険があるか知る。
b 内部環境分析・・・自社の持つ経営資源や能力を分析し、アイデンティティ、強み、弱みを明確にする。
c 戦略の代替案立案・・自社にとって多くのチャンスをものにするような事業分野を探す。一方で、自社のリスクになりそうな事態を予測し、弱みを補強する。
d 戦略の選択・・・投資収益率や株主価値を高める戦略を選択する。
e 戦略の実行・・・戦略の実行に関わるメンバーのコミットメントを引き出す。
f 戦略のレビュー・・・目標の達成の程度を調べる。また、経営使命やビジョンへの影響度を調べる。
|
| 4. 経営戦略のポイント |
(1)自社の事業機会
a 選択と集中・・・経営資源を強みのある事業へ集中する。強みを失ったときは、リスクが大きくなる懸念あり。
b 経営資源の余剰の使い道・・・経営がうまくいき、経営資源が企業内に余っているときは、新しい分野へ投入することでよりいっそうの成長を図る。
(2)独自性のある強みを活かす
a 自社の独自性を活かし、他社との競争に打ち勝つ
b 独自性を保持できるよう投資をしていく
c 独自性を強みにするような事業や顧客を選択する
(3)経営戦略は変化していくもの
a 経営戦略は固定的なものではなく、環境変化によって修正されねばならない
b 戦略の定石は生まれるものの、成功パターンに固執しない
(4)業界内のポジショニング
a 業界内における競争力のあるポジショニングを獲得する。もっとも望ましいのは市場でNo.1。
b ポジショニングは企業の独自な競争力で形成される。
|
 |
|
 |