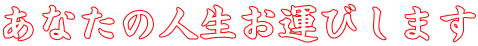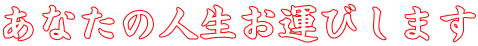第4回 起業の準備
|
| 第4話 「涙の旅立ち・・・愛娘の就職」 |
(1) あらすじ
口コミで評判を呼び、上原運輸の引っ越し部門の業績はアップ。トラック1台で仕事をするのはギリギリの状態に。上原賢太郎の幼なじみ達の商店と提携し、引っ越し客からの注文をとりまとめるサービスも展開している。上原真喜の発案から始まったこのサービスは、各店の売り上げを伸ばし商店街を活気付かせることになった。
ある夜、有名な割烹「有吉」から引越の依頼を受ける。「有吉」では父、祐市は娘の荷物を今すぐ運び出してくれ、と言い捨てて出て行く。フランス料理の勉強がしたいという娘の夢を祐市は認めず、話し合いが物別れに終わったのだという。後日、上原夫妻は「有吉」を訪ね、上原夫妻と有吉の主人は娘が修行をする六甲のレストランへ行くことになり、そこで親子は再会する。
(2) ドラマのポイント
a 上原運輸が儲かると、幼なじみの実家の商店も儲かるようになっているが、なぜ、そうしているのか?
1970年代の大阪下町ならば隣近所の助け合いといった文化を残していると考えられる。こうした地域では一人勝ちしていると足を引っ張られるので、共存共栄の戦略が望ましい。また、引越業は個人客を相手にしているので、口コミの効果などを考えると、他の商店に利益を落とし、顧客を紹介してもらうことも必要。このドラマに関して言えば、他人を大切にし、喜びを分かち合おうという真喜の性格もあるし、幼なじみに仕事を手伝ってもらっているということもある。
b 助ちゃんは引越業に賭けようと思ったのか?
ポイントは3点あると思う。真喜と一緒に仕事をしたいということ、第二に引越業の未来に賭けてみたいという気持ち、第三に公衆浴場という商売の将来を悲観的に考えているからである。
c 真喜たちが有吉の主人に行った行為はビジネスとしてどうか?
企業が成長すれば多くの顧客と出会う。その時、こうした顧客の人生を解決するビジネスのやり方ができるかどうか? 顧客によってサービスが変わるのは良くないため、友人や知人としては真喜の行為は良いかもしれないが、商売人としてはあまり良いことではない。
d なぜ、賢太郎は上原運輸の社長を真喜へ譲ろうと考えたのか?
経営者としての資質と能力、ビジョンを創造し、意思決定し、人をまとめていく能力は、真喜の方が優れていること。引越業に賭ける情熱は真喜の方が強くこと。引越の仕事が生活産業であるため、女性の方が優れたアイディアを出せそうなこと。
|
| 2. 起業に当たって |
(1) 自分の動機を再確認しよう
a なぜ起業するのか?→起業して何を実現したいのか?→どうしてそれを実現したいのか?
b 起業をできるか?→できる理由とできない理由を探す
c 起業することで幸せになれるか→なれる理由となれない理由を探す
d その事業で他人や社会に喜ばれるか→喜ばれる理由と喜ばれないかもしれない理由を探す
e 起業することが現状より良くなるか→良くなると思う理由と良くならないと思う理由を探す
(2) 自己分析
a 起業家としてやっていける性格か、自己分析をする。例えば、目標は必ず達成する、失敗してもめげない、仕事漬けの毎日にも耐えられる、など。
b 仕事と結びつきやすい資格や能力を持っているか。例えば、弁護士や会計士といったその資格を持っていると専門家として活躍できる。古物商、調理師といった資格がないと開業できない商売もある。資格ではなくても技術や営業の能力を持っていると、それを武器に起業できる。
c 起業したら支援してくれる人たちがどれだけいるか?
d 起業するとき、使えそうな資産を持っているか?例えば、資金、施設、設備、商品など。自前で持っていなくても、簡単に手に入れられると良い。販売しようとする商品を安く仕入れられるというのも強みになる。
(3) 起業する分野
a 経験や知識がある分野…予備知識やこれまでの能力、資産が活用できるため、リスクが低いものの、他者との差別化が甘くなりがち。その分野の競争が激しかったり、成長性がなかった場合、起業後が苦しい。
b 未経験の分野…高成長や高収益性が見込めたり、ニーズを発見しての起業の場合、経験がない分野で起業することもある。その場合、同業者で修行する、事前に情報を収集し、研究するなどの、準備をすべきである。また、ラーメン店など、FC(フランチャイズ方式)で事業ノウハウをパッケージで獲得することも可能な事業もある。
(4) 周囲の理解を得る
a 家族や親戚の理解を得る…資金調達でも、労働力でも家族や親戚へ依存することもある。将来が不確実な起業をすることで生活が一変し、家族に負担をかけるかもしれない。起業する気になったら、家族や親戚に納得してもらえるよう、十分なコミュニケーションが必要である。
b 勤務先の理解を得る…仕事を持っていて、そこから独立する場合、起業によって辞める勤務先の理解を得ておくことも重要である。特に同じ分野で起業しようと考えているのであれば、勤務先と良好な関係を保って独立し、仕事を回してもらえるくらいが望ましい。
c 取引先の理解を得よう…仕事で知り合った取引先や知人の理解を得ることで、起業後、支援してくれるかもしれない。特に顧客を起業前に確保しておくと成功する可能性は高めるため、可能性のある顧客には起業を決める前に事前に相談してみる。
(5) 許認可
事業によっては行政の許認可が必要である。規制緩和の時代とはいえ、許認可が必要な業種は1,000件を超える。また、許可条件が地方自治体や地域ごとに異なる。許可や認可に時間がかかる場合もあるので、事業内容が見えてきたら、事業場所の地方自治体の商工部(経済関係の部門)に尋ねてみよう。
例
| 業種 |
区分 |
窓口 |
| 飲食店 |
許可 |
保健所 |
| 食料品の販売 |
許可 |
保健所 |
| ペットショップ |
届出 |
保健所 |
| 理容院・美容院 |
確認 |
保健所 |
| ゲームセンター |
許可 |
警察署 |
| 深夜飲酒店 |
届出 |
警察署 |
| 宅地建物取引業 |
免許 |
都道府県 |
| 保育所 |
許可 |
都道府県 |
| 旅行代理店 |
登録 |
運輸局 |
| 酒類販売業 |
免許 |
税務署 |
(6) 起業に必要な6S
a 信念
b 製品
c 市場
d 仕組み
e 資金
f 支援
|
| 3. 起業形態の選択 |
(1)個人事業
a 税務署や監督官庁がある場合はその官庁へ開業の申告をして、起業できる。もっとも簡単な起業形態。
b 個人事業で行った事業収入は個人の所得となる。税金の申告は白色申告と青色申告がその違いは、複式簿記による記帳義務の有無。青色申告は面倒な記帳義務があるものの、家族を従業員として扱える青色専従者の特典、純損失の繰り越し控除や特別控除の特典がある。
c 借金や資産の取得は全て個人に帰する。そのため、経営責任は無限責任となる。
d 累進課税と法人税率の比較で1,000万円以内の事業所得であれば、個人事業の方が良いかもしれない。
(2) 商法法人
a 現在は合名会社、合資会社、有限会社、株式会社の4形態あり、それぞれのメリットとデメリットがあるものの、平成17年度くらいに商法改正が予定され、大幅に変わる模様。
b また、「中小企業挑戦支援法」によって、最低資本金に特例が認められ、5年以内に最低資本金を満たすことができれば、実質的に最低資本金の制限はなくなった。
| 区分 |
合資会社 |
有限会社 |
株式会社 |
| 最低資本金 |
規定なし |
300万円 |
1000万円 |
| 出資の内容 |
労務や信用も可 |
現金と現物のみ |
現金と現物のみ |
出資者の
責任範囲 |
無限責任社員と
有限責任社員 |
出資額の範囲内 |
出資額の範囲内 |
| 取締役 |
必要ない |
1人以上 |
3人以上 |
| 監査役 |
必要ない |
いなくても良い |
1人以上 |
| 代表取締役 |
必要ない |
いなくても良い |
1人以上 |
| 取締役会 |
必要ない |
省略できる |
開催が必須 |
| 役員の任期 |
制限なし |
制限なし |
取締役2年以下
監査役4年以下 |
| 総会 |
必要ない |
総社員の同意で
書面でもよい |
開催は必須 |
| 最高決議機関 |
無限責任社員 |
社員総会 |
株主総会 |
| 決算の公告 |
必要ない |
必要ない |
決算期ごとに行う |
| 出資分の譲渡 |
無限責任社員全員
の同意必要 |
社員間は自由。
社員外は社員総会
の承認が必要。 |
原則自由 |
| 組織変更 |
全社員の同意で
合名会社へ変更。 |
社員総会の特別決議
により株式会社へ。 |
株主総会の決議で
有限会社へ。 |
| 世間体 |
なにそれ? |
小さな会社 |
信用できる |
(3) NPO法人
a 1998年に生まれた新しい法人格。民間の公益法人。社会貢献を事業にする場合、この形態を選択する人が増えた。
b 事業領域が17(保健・医療・福祉、社会教育、まちづくり、学術・文化・芸術・スポーツ、環境保全、災害時の救援、地域安全活動、人権擁護・平和推進、国際協力、男女共同参画社会推進、子供の健全育成、情報化社会の発展、科学技術振興、経済活動の活性化、職業能力開発や雇用機会の拡充支援、消費者の保護、上記活動に対する支援)に制限されている。
b 法人設立には都道府県か内閣府の認証を受けて、登記を行う。認証先に年1回、活動報告書を提出する。
(4) 企業組合
a 個人事業者や企業が4人(社)以上集まって、出資をして作る組合形式の事業体。
b 最低出資金の制限はないが、設立に当たって4人以上の出資者(企業も可)
c 組合員は出資金の多寡にかかわらず、議決権は平等。組合員の1/2以上が組合事業に従事する必要がある。
d 認証ですむNPO法人と違い、企業組合は都道府県の認可が必要。
e 設立後に、組合員の議決によって有限会社や株式会社へ変更可能。
(5) 各形態の主な相違比較
| 区分 |
個人事業 |
株式会社 |
NPO法人 |
企業組合 |
| 開業資金 |
制限なし |
1000万円以上 |
制限なし |
制限なし |
| 設立手続き |
易しい |
やや煩雑 |
やや煩雑で
時間もかかる |
やや煩雑で
認可がある |
| 資金調達 |
出資は困難。
融資と利益の
蓄積が中心。 |
出資、融資、
利益の蓄積。 |
会費収入、寄付、
補助金、事業収入
の蓄積、融資。 |
出資、融資、
利益の蓄積。 |
| 責任範囲 |
無限責任 |
出資分内での
有限責任 |
出資の概念がない
ので、規定なし。 |
出資内の
有限責任 |
| 会計処理 |
白色申告なら
簡便 |
複式簿記 |
単式簿記でも可。
公会計に近い。 |
複式簿記 |
| 税金 |
所得税、
地方税 |
法人税と事業税 |
本来事業以外の
事業には企業と
同様の税金 |
企業と同じ |
|
 |
|
 |