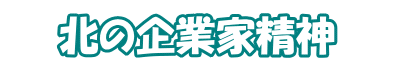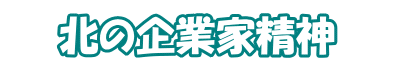① ベアリング商社からベアリングメーカーへ
北海道で世界的ベアリングメーカーを作り上げた小林英一氏は1931年に東京で生まれた。幼少期に父親を亡くしたため小林氏は自立心を少年期から持ち、起業の夢を持っていた。小林氏は都立大森高校を卒業し、1949年にベアリング専門商社の城北ベアリング商会へ入社する。このベアリング商社への入社がその後の成功へつながる入り口であるとは、入社当時は思わなかったようである。入社後の小林氏は持ち前の自立心と熱心さによって営業で頭角を現した。1953年に城北ベアリング商会は、当時花形産業であった石炭産業へベアリングを売り込むために、北海道札幌市に出張所を開設することになり、小林氏は石炭産業への事業機会の大きさに魅力を感じて札幌行きを志願する。札幌出張所は3人でスタートしたが、その営業力を買われて入社4年の小林氏が社長に抜擢された。北海道は広い面積を持つため営業コストがかなりかかるが、城北ベアリング商会は大手ベアリングメーカーの販売商社ゆえにマージンはそれほど厚くない。その結果、小林氏の営業力で順調に売上高は増加しても、採算的には出張所の業績は厳しかった。そんな状況の下、1959年に転機が訪れる。本社から営業所長であった小林氏へ札幌出張所をスピンオフさせ、小林氏に営業譲渡したい意向を伝えてきた。事業を興す夢を持っていた小林氏にとって、会社の申し出は千載一遇のチャンスであった。小林氏は資金をかき集め「城北商事」を設立して社長へ就任、出張所の営業を継承した。従業員は5名と小所帯からの出発であったが、大きな成功の第一歩を踏み出したのである。
炭坑会社へのベアリング売上は石炭産業が順調であったが、小林氏は城北ベアリング商事の札幌出張所所長時代から北海道の市場に対しては、顧客と想定される有力な機械メーカーや電機メーカーが少ないため、懐疑的であった。また、石炭も石油という新しいエネルギーに主役を奪われ懸念があったため、城北商事の経営戦略は札幌出張所のものを継承するのは難しいと小林社長は判断していた。それは札幌にやって来てから10年間は試行錯誤しながらつかんだ結論であった。そこで、市場を北海道外にも求めることにしたが、日本国内におけるベアリング販売競争は激化していたので、海外に目を向けることにした。小林社長は今でこそ世界を相手に通訳なしでビジネスを行っているものの、当時は英語もできず、小林社長の海外進出戦略に対して無謀という声が挙がっていたが、本人は意に介さなかった。英語を独学で学習し、1960年代の中頃からアメリカやヨーロッパでで飛び込み営業を行ったが、当然ながら最初はなかなかうまくいかなかった。それでも日本製ベアリングの品質の良さと安い価格を武器に、少しずつ顧客を増やしていった。そして、いつしか販売だけでなく、自らが川上である製造へ進出し、世界一のメーカーを作る夢を持ち始めるようになっていた。
1969年、小林社長は夢に一歩踏み出すことになった。小林社長個人、城北商事、三井鉱山の子会社三機製作所が共同出資をして、小径ベアリングを生産するメーカーを芦別に創業することになったのである。炭坑の街として栄えた芦別も石炭需要が先細りとなって、閉山が相次ぎ始めた。北海道では最大の顧客であった石炭会社が斜陽化すると共にベアリングの需要も減少し、ベアリング専門商社を経営する小林社長は危機感を抱いていた。そうした危機感を持っていたときに、三井鉱山芦別鉱業所の鹿野所長と、三井鉱山の子会社である三機製作所の高木社長に相談した。三井鉱山も炭坑離職者対策のために新規事業を考えていたため、小林社長のメーカー創業計画を支援することになり、資本金1,000万円で「北日本精機株式会社」を芦別市に設立した。出資者は小林社長、城北商事、三機製作所で各1/3ずつの出資比率であったので、実質的には小林社長が経営の実権を握っていた。本社工場は、西芦別の炭坑病院を改装して使用することになった。芦別の地を選んだ理由は、三機製作所から生産技術ノウハウを導入するため、同社工場に近い方が便利であること、炭坑離職者という労働力確保が容易であったこと、生産のみを行うため芦別でも不都合がなかったのである。また、小林社長が芦別を気に入っていたことも大きな理由であったようである。北日本精機の代表取締役社長には主にベアリング生産技術を担当する高木三機製作所社長が就任し、小林城北商事社長は代表権を持つ専務取締役に就任して主に営業部門を統括することになった。小林氏個人と自らが経営する会社で2/3の株式を抑えながら、小林氏が社長に就かなかったのは、生産に関する知識が十分でなかったこと、高木社長からいろいろ学んでいたこと、年齢的に若かったこと、三井鉱山の力を活用したかったからなどが考えられる。帳簿上の販売先は小林氏が経営する城北商事で、城北商事が北日本精機製のベアリングの営業を行う製販分離の形態を取った。
② 世界市場での優位性構築
北日本精機は当時の大手ベアリングメーカーとの競争を避けるため、40mm以下の小径ベアリングと極小ベアリングに絞った。当時は自動車向けなどの標準化されたより大きな径のベアリング製品の市場が大きく、大手ベアリングメーカーは生産効率を高めるためこの市場向けの製品を生産していた。一方、小径ベアリングや極小ベアリングの市場はカスタマイズされた製品の需要が多いため、小ロットで生産効率は良くないため、大手があまり手がけたくなかった市場だったのである。炭坑閉山対策のための経済的支援を受けて、大手ベアリングメーカーの使っていた最新鋭の機械を導入し、生産を開始した。機械は大手メーカーと同じでも、工場の生産技術は同等でないため、北日本精機の製品品質が大手と同等になるまでに5年の時間を要した。一方、小ロットの高いコストも、習熟効果などで少しずつ低下していった。また、炭産地振興政策の一環として生産設備の特別償却が認められていたため、他社と比較して最新の生産設備へ更新するサイクルを短くできたのも、製品の競争力を高める一因となっていた。競争の少ない市場で、品質が良くなり、価格が折り合えば、順調な販売が見込めたが、日本ではブランドの確立できていない中小企業が高いシェア取るのは難しい。そこで、城北商事が開拓した海外の販売先に積極的に売り込んだ。ニクソンショックなどで円高に振れたものの、日本からの輸出のコスト優位は十分であり、また、品質の高い小径ベアリングや極小ベアリングなどを生産している企業も少ないため、まず、東南アジアで着実に売上を伸ばしていった。1977年には欧米へ正式に輸出を開始し、特に米国での医療機械や精密機械に使用される極小ベアリングの販売に力を入れた。欧米での輸出の成功により、城北商事を通じての北日本精機の輸出比率は一時期8割まで高まった。こうした海外市場における北日本精機の高い評価から、日本の大手ベアリングメーカーは同社とOEM(相手先ブランドによる生産)による取引を始めるようになっていった。
市場の開拓が成功を見せていた1978年、高木北日本精機社長が退き、小林北日本精機専務が代表取締役の地位へ就任した。高木前社長の下で生産管理を学ぶ一方、営業面での成功をバックに、満を持した社長就任と言えよう。小林社長は積極的な成長戦略を採用する。1980年に、製品出荷に利用していた新千歳空港により近い、栗山町に月産20万個の生産規模の工場を新設した。そして、1981年に、西芦別の本社工場とは目と鼻の先にある上芦別の芦別工業団地に23万平方メートルの工場敷地を購入した。ここにベアリング焼き入れ、研磨の工場を建設して、操業を開始した。西芦別と上芦別の稼働によって、西芦別本社工場、栗山工場と合わせて月産100万個の生産体制が確立した。製品は大手ベアリングメーカーと比較して多品種であったが、世界へ販売することでなるべく量を確保し、コストを低下させる戦略であった。新工場が稼働し始めたことで、1982年から旧態化してきていた西芦別地区の旧本社工場から上芦別地区の工場へ生産設備の移転を開始する。1983年1月、北日本精機の営業を一手に引き受ける城北商事はオランダのエンジニアとの共同出資でスイスにマーケティング会社「ヨーロッパ・エゾ・ベアリング」を設立した。これは当時のEC(ヨーロッパ共同体)が日本製ベアリングに対するダンピング課税を逃れるためと、ヨーロッパ市場の情報を収集する目的であった。新工場の稼働の恩恵で月産100万個になり、1983年1月期の売上高は約17億円に達していた。輸出は城北商事を通じて70万個程度である。小林社長が社長職を兼務し、北日本精機の親会社で営業部門であるサッポロプレシジョン(旧城北商事)の競争優位の源泉は情報収集力と情報伝達力と考えられていた。同社の情報収集は維持コストの高い海外支店を持たず、情報源は世界18カ国26社の現地ベアリング輸入会社であった。小林社長はこうした輸入会社のトップと直接コンタクトを取ることで市場の情報を自ら集め、北日本精機の経営上の意思決定へ迅速に反映し、激しい競争の中で市場シェアを高めていった。1983年12月には、炭産地への振興基金や日本開発銀行など政府系金融機関からの低利子融資を利用して総投資額25億円の末、本社工場が完成し、生産能力は月産100万個から130万個へ、そして1984年6月には180万個へ拡大された。北日本精機の企業規模からすればかなり思い切った生産拡張戦略であったが、小林社長の豊富な情報と市場分析力によって導き出された合理的な意思決定であり、また炭産地である芦別への手厚い経済支援による資金調達コストがあったため、生産拡張によるリスクは低められていた。
1984年1月、北日本精機は超薄型ベアリングを開発した。市場動向の様子を見ることとと生産品質の確立のために、当面は月産10万個で、大部分は米国機械メーカーへ輸出することになった。価格は従来品の2倍以上の1個200円で、同社以外のライバル製品がなかったため収益性も高かった。翌2月、西芦別工場から上芦別工場へ徐々に生産設備を移転していたが、その作業も完了し、最新鋭の、上芦別の工場に生産統合することで生産性を改善した。生産能力も月産は120万個になり、自動化率は30%であった。国内向けOEMが増加したため、輸出比率は多少低下してきていたが、それでも6割をサッポロプレシジョン経由で輸出していた。1985年5月、ベアリング生産の前工程である小径軸受を行っている和歌山県の株式会社潮岬製作所の株式をサッポロプレシジョンと北日本精機で6割取得し、系列化する。北海道から離れた和歌山県に立地する工場故に物流面で不利になるが、他社の系列下から離れることになった潮岬製作所の技術力を高く評価したからである。そして、翌6月には、北日本精機が300万円、サッポロプレシジョンが600万円、残りを小林英一北日本精機社長と佐藤栄基氏が出資し、資本金2,000万円で芦別精機を設立した。北日本精機の関連下請会社として丸棒鋼からリングを削る旋削を担当することが事業内容である。北日本精機の施削部門の生産能力が限界になっていたから、その部門の増強のために北日本精機の幹部であった佐藤氏を代表取締役社長に据えて新会社を立ち上げたのである。芦別精機は北日本精機の本社工場に隣接した土地に工場を建設し、操業を開始した。
プラザ合意以降、円高ドル安が進行し、北日本精機の主力としている小径ベアリングや極小ベアリングの国内価格は安い輸入品の流入の影響により下がる一方、円高分全部を価格転嫁できないため輸出の採算性が低下していた。そのような状況に対応して、全社的にコストの見直しを行い、15%程度のコストダウンに成功していた。そして、1987年1月、10,000~20,000個の小ロットの多品種少量生産に対応できる全自動の標準ベアリング組立ラインを開発し、稼働させ始めた。新ラインでは工具を取り替えるセット換えを従来の1/20以下の2時間に短縮でき、ライン単位の労働者数も半減できるため、生産コストは3%程度低下させることが可能になる。また、完成品のチェックも自動化することに成功し、自動化率は90%に達することになった。同社の生産能力は月産200万個であったが、新ラインの導入で月産300万個の能力を持つことになり、それに合わせて前後の工程の生産能力を増強することにした。1988年1月期の決算では、売上高25億円、月産242万個を達成していた。過去5年間に20億円の設備投資を行ってきた結果が、生産能力の大幅な拡大につながっている。国内向け販売に関しては全体の5割弱で、国内大手メーカー向けのOEMがそのうち8割を占める。輸出向けや国内のOEM以外の販売では、北海道を示す「EZO」というオリジナルブランドで出荷していた。生産の拡大によって、従業員は280人まで増加していた。翌1989年1月期は、内需拡大の恩恵で、売上高は急拡大し、34億円に達していた。1989年5月にはいっそうの成長を狙うべく、1991年までには生産能力を250万台から300万台へ拡大する計画を立案した。本社工場を1,000平方メートル拡張し、7,000平方メートルへ、最新鋭の工作機械を22台導入し、従業員も30名増やして310人にする計画である。当時の北日本精機では、1年間に1,000種類のベアリング生産し、年1割程度種類が増加している状態で、多品種化が進展していた。また、コンピュータや産業機械向けの薄型ベアリングや大型ステンレスベアリングの需要が増加し、そうした需要動向に対応するための生産設備増強であった。結局、増設した新工場は1992年10月に完成し、稼働を始めた。建物の建設費と内部の機械設備を含めて10億円の投資になった。一方、生産設備の増強に合わせて物流の効率化のために、配送センターを工場の隣接地に新設し、同年5月に完成した。今まではサッポロプレシジョンが札幌でベアリングの包装を行っていたが、配送センター完成後はそこで包装を行い、そのまま出荷できる体制にする。配送センターの新設による総投資額は約3億円であった。
③海外生産開始
1990年1月期の北日本精機の業績は、売上高37億円、経常利益8億円に達していた。積極的な設備投資と特別償却で減価償却費も多いが、高付加価値の製品で高い市場シェアを獲得していることで高い収益性をあげていた。ただし、ベアリング製造だけに依存するリスクを減らすために、本業の好調さを背景にして、これまでのベアリング生産技術を活用した新製品の開発と製造へ5年以内に乗り出すため、社内に新製品開発室を設置する事になった。一方で、海外での事業展開は、それまで中国の上海の協力工場でベアリングの一部を月産80万セット生産していたが、輸出競争力を一層高めるために生産コストの低減を狙って、積極的な海外生産戦略を取り始めた。まず、1990年7月に韓国での現地生産を決定した。93年度中に工場を投資額4~5億円で、93年度中に工場を建設し、年間輸出額が3億5,000万円の韓国国内向けと東南アジア向け製品の生産をこの工場で行う計画である。しかしながら、小林社長は中国市場の成長可能性に目を向けて、上海で93年中に工場を建設し、現地で施削、研削、組立、検査まで一貫生産することを決定した。協力工場向けにベアリング製品の部品供給も行う。上海で操業を開始するこの工場の規模は2,000平方メートルと大きく、東南アジア向けの標準量産品の生産拠点になるため、韓国での現地生産計画は見直されることになった。中国で新工場が稼働した後は、日本国内の工場は主に日本と欧米向けの高精度で付加価値のベアリング製品生産に特化し、海外工場と役割分担をすることになる。1993年9月に上海精密有限公司を北日本精機の全額出資で設立し、翌1994年3月に上海工場の建設に着工し、総投資額3億円で5ヶ月後に完成した。9月からの新工場の稼働により、中国での生産は月産100万個で、コストは日本国内で生産して輸出するより3割程度減少する見込みであった。初年度の決算でも5,000万円の黒字になり、低廉な労働力のメリットが十分に生かされた。その後も、日本からの米国向け輸出に対するダンピング課税などの問題が生じたため中国から米国へ輸出するようになったり、急激な円高によって中国生産の相対的コスト優位が高まり、中国での事業拡大が促進されていった。中国工場の稼働によって北日本精機グループはコスト優位を高め、$1=\100円以下の円高でも採算性を確保できる収益構造を作り上げた。1995年6月、ベアリングに組み込む精密鋼球(スチールボール)の生産工場を上海で年内に建設を着工することに決定した。精密スチールボール大手の大旺鋼球製造と北日本精機の現地子会社が半分ずつの出資で資本金3億5,000万円の合弁事業形態で行うことになった。上海工場で必要とする精密スチールボールの供給を行い、上海工場で使う部品の現地直接調達を可能にし、5%のコストダウンを図る。同年10月から上海工場は後工程だけでなく前工程も行うことで一貫生産を完成し、生産を効率化、価格競争力を高める。また2億円程度の投資で上海工場単独で月間生産量を100万個へ拡大させる。1996年3月では、上海工場の月産は220万個、従業員300人体制と本社工場並の生産規模へ拡大していった。1998年、上海工場では研磨機の修理工場を2億円で建設し、中国での事業を強化することにした。上海工場の事業はほとんどを現地スタッフが運営し、事業も中国国内で多くは完結し、経営の現地化がいっそう進むことでベアリング納入先からのコストダウン要求に応えられる体制を整えた。また、まだ具体的な計画は公表されていないものの、インドでの生産が検討されており、北日本精機の海外戦略は21世紀に入っても積極的に展開されるようである。
1993年4月、三井石炭鉱業所の閉山に伴う離職者対策の意味合いもあり、三井石炭と共同出資で「北日本ハイプレシジョン株式会社」を資本金2,500万円で設立した。北日本精機は1,500万円を出資し、小林北日本精機社長が会長、田島高基三井鉱山中央研究所次長が社長へ就任した。当初は資本金1億円で会社を設立し、工場用地取得を含めた総投資は11億円の計画であったが、個人消費財向け小型ベアリングが景気下降から販売単価を下げるという経済環境の不透明さから資本金を2,500万円へ減らしてスタート。工場建設も棚上げして、北日本精機工場内を間借りし、3億円の機械設備への投資で操業開始した。北日本精機が行った北日本ハイプレシジョンへの出資は、同社の生産設備増強戦略の一環としてだけで捉えると本質を見誤るかもしれない。確かに炭坑離職者のために新会社を作れば、旧炭産地向け振興対策から経済的支援を受けられるメリットがあることはたしかである。しかしながら、小林社長は以前から地域社会への貢献に対して熱心であり、炭坑閉山に伴う地域社会の衰退を食い止める意図もあって新会社を作り、雇用機会を創出した側面もある。こうした小林社長の理念は、北海道アサヒの事業を引き継ぎ、新会社芦別ゴムを作って工場を再開した行動にも表れている。1998年6月に親会社アサヒコーポレーションの倒産に伴って破産宣告を受けた北海道アサヒの旧工場を北日本精機が8,500万円で取得し、北海道アサヒの事業を継承するために設立された芦別ゴムへ無償で貸与し、経済的支援を行った。こうした日本精機の支援の下、芦別ゴムとして75人体制で操業再開し、再建中のアサヒコープから受注生産を受け、事業を継続した。小林北日本精機社長が芦別ゴムの代表取締役会長へ就任し、単に経済的支援をするだけでなく、経営責任も取る姿勢を示している。こうした地域社会への貢献もあって、北日本精機および小林英一社長は単なる成功者としてではなく、地域社会から尊敬されている企業であり、個人として認識されていると思われる。また、雇用機会の少ない芦別で300人の従業員を雇用し、事業税などを多く支払う、国際的企業と言うことで、地域社会から支持は非常に強いようである。
地域社会の貢献は、本業の業績が良いから可能であるが、1994年1月期の北日本精機の売上高は36億5,700万円、経常利益1億500万円であった。ベアリングの種類は800種以上あり、その中で超薄型ベアリングで世界市場のシェアは8割、フランジ型で5割の世界市場シェアを持っている。国内だけでなく海外27カ国で販売し、グループ会社は国内8社と海外2社にのぼり、グループ売上高は160億円に達していた。海外での販売が多いため、1995年12月に国際的品質マネジメントシステムであるISO(国際標準化機構)9001の認証を北海道の製造業として初めて取得し、欧米の取引先からの品質要求にISO応えられる体制を整えた。1999年11月には、これも北海道内で初めて環境マネジメントシステムに関するISO14001の認証を取得した。ISOの認証を取るためには、数多くの手順マニュアルを整備し、その手順で日常業務を行わなくてはならず、北日本精機の高い管理能力を示した。
1990年代中盤から大きな勢いを持ったIT革命によって、コンピュータ関連の需要増加し、コンピュータに使用されるベアリングの需要は高い伸びを示していた。1995年当時の芦別工場は月産490万個、栗山工場は月産50万個の生産規模であったが、1998年度には月間700万個へ引き上げるために30億円の投資を行うことに決定した。上海工場も月産80万個から3年後の1998年には月産400万個レベルへ引き上げる計画を立てた。1996年2月に工場に情報化したインテリジェントビルを総事業費6億円で建設する計画を発表し、翌年2月に完成させた。いちはやくITによる工場および管理部門における生産性のいっそうの改善を図ったのである。世界的なパソコン向け需要の増加からいっそうの生産規模の拡大に迫られ、総投資額10億円で本社工場を増設し、生産能力を現行の月産800万個から2002年には5割アップの1,200万個体制にする計画が2000年になって立案された。ITを活用してリアルタイム集中管理などを行い、価格競争の激しい市場で競争力を高め、市場のリーダーとしての地位を揺るぎないものにする戦略である。
|